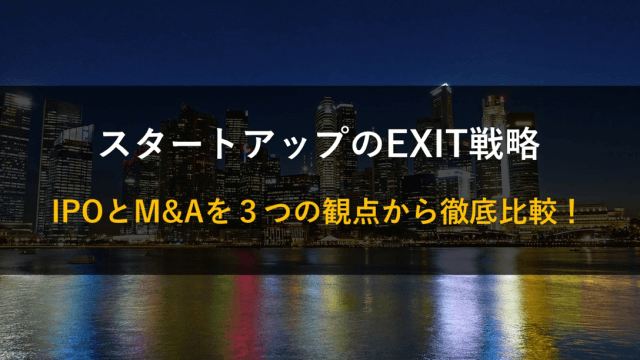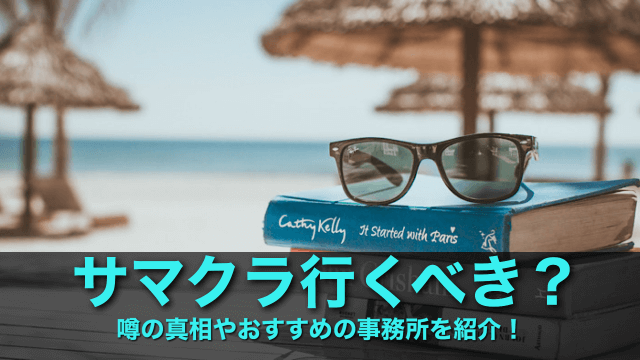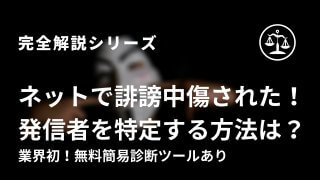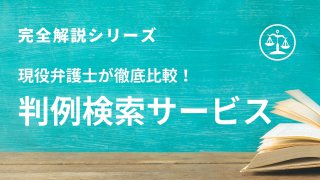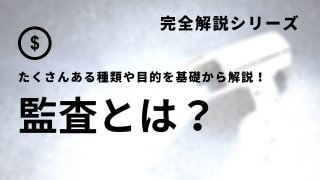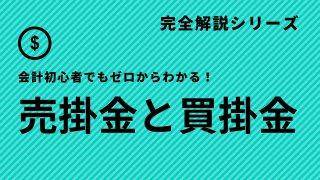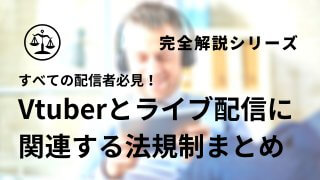M&Aにおいて、財務・税務手続きは必ず行わなければなりません。
その財務・税務の手続きは、税理士に依頼するべきという事はご存じでしょうか?
M&Aと税理士はあまり結びつかないイメージかもしれませんが、税理士に相談する事により、M&Aをより満足度の高いものとすることができます。
今回は、税理士ならではの役割と依頼するメリットについて詳しく解説していきます!
目次
1.M&Aとは

M&Aとは端的にいうと、企業の買収や合併のことを指します。
一般的には創業者や投資家が会社を売る側となり、買い手との間で株式譲渡契約などを交わします。
M&Aの成立まで様々な手続きがあるのですが、中でも重要なのが、買い手企業が売り手企業を調査するデューデリジェンスです。
デューデリジェンスの主な調査内容は「企業・事業の資産価値」「M&Aによるリスク」「予想される収益」などです。
通常、買い手と売り手の基本合意の後、デューデリジェンスが実施され、最終契約が締結されます。
M&Aは、売り手にとっては創業者利益やキャピタルゲインをもたらすイグジットとして、買い手にとっては既存企業とのシナジー効果をもたらすものとして、昨今は企業規模や業種にかかわらず活発に行われています。
また、M&Aには節税を見込める場合があります。
たとえば、買収先の企業に過去の繰越欠損金が積み上がっている場合、その欠損金を自社に計上すると、黒字であれば利益額を圧縮できます。
課税の対象となる金額を小さくできるため、節税効果が得られるケースがあるのです。
M&Aに関する基礎知識は、こちらの記事からご覧いただけます。
2.M&Aにおける税理士の役割
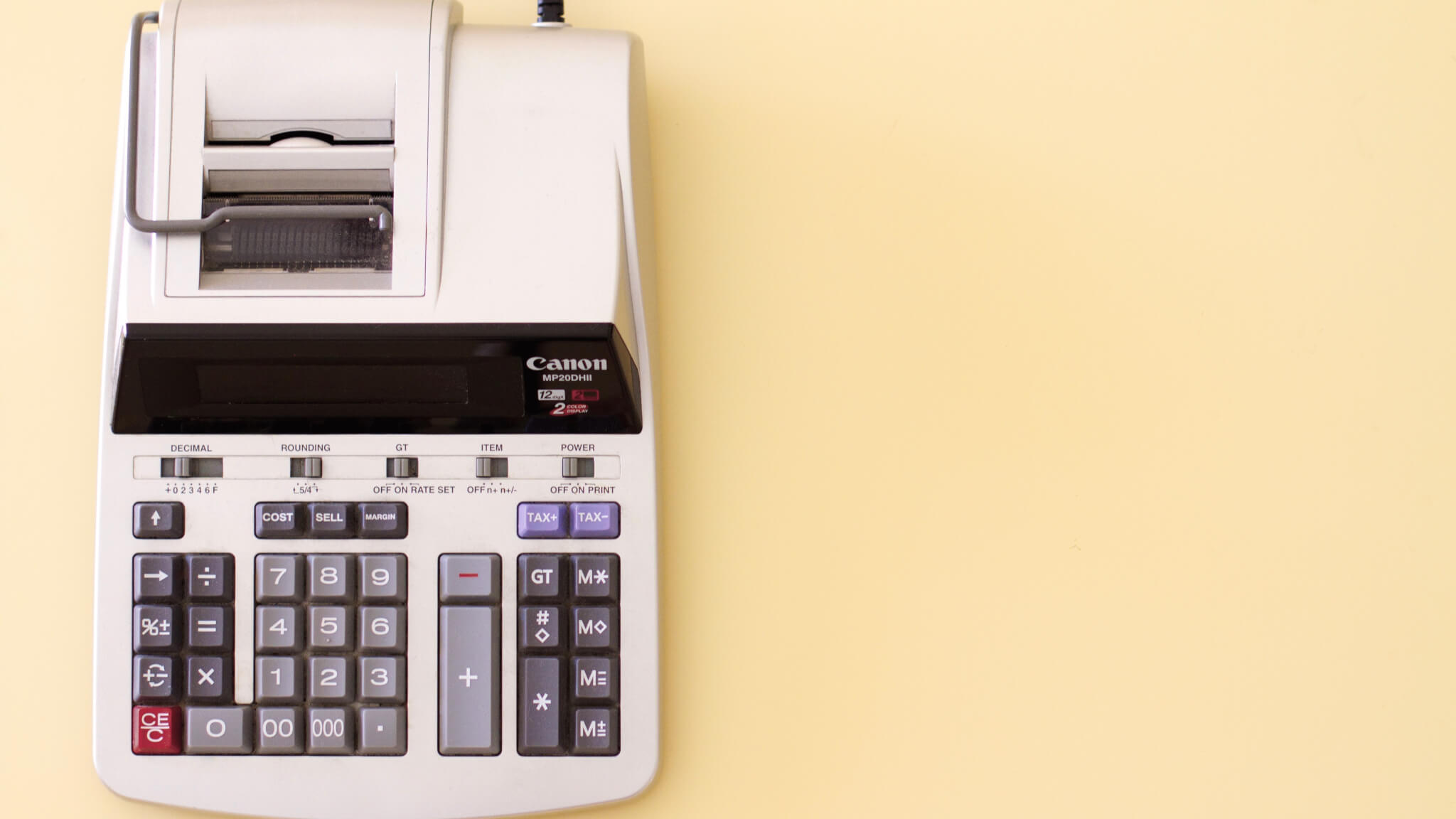
ここからは、M&Aにおける税理士の役割について、具体的に説明をしていきます。
M&Aの前後を問わず企業の税務面をサポートしてくれる税理士ですが、今回は代表的な役割として3つのポイントに絞ってみていきます。
(1)バリュエーション
バリュエーションとは、会社の株式や保有資産の価値、すなわち企業価値を評価する行為です。
M&Aにおけるバシュエーションには、売り手側企業に対する適正な買収価格を算出する目的があります。
これは、いずれか一方当事者のみによって行われるのではなく、売り手側は売買価格提示のため、買い手側は買収を本当に行うか決定するために、双方がバリュエーションを行います。
そして、バリュエーションの結果をもとに条件を検討し、双方の希望をもとに交渉が行われることになります。
上場企業であれば、株価は市場の動向によって決せられるため株価の算出が容易である一方、ほとんどのベンチャースタートアップのような非上場株式は公開されておらず、市場価値を算出することが困難です。
そのため、こうした企業のM&Aにおいては、専門家による客観的なバリュエーションがM&A成立のために重要となります。
多くの場合、バリュエーションは、公認会計士や税理士などのM&Aに精通した専門家により行われます。
算出基準としては、財務諸表の純資産(コスト)や、将来的な予想利益やキャッシュフロー(インカム)、既存他社や取引(マーケット)などが用いられます。
バリュエーションの種類については、こちらの記事もご覧ください。
(2)デューデリジェンス
デューデリジェンスとは、M&Aの契約前に売り手企業に対して行われる様々な調査のことであり、M&Aを成功さたるめには絶対に欠かすことのできない、非常に重要なステップです。
法務やビジネス面など、それぞれのプロフェッショナルによる専門的な視点から、企業について事細かく調査が行われます。
その中でも、財務デューデリジェンスや、税務デューデリジェンスは税理士によって行われるデューデリジェンスです。
税理士は、財務・税務デューデリジェンスの際、会計・税務の専門家として売り手企業の分析を行います。
具体的には、簿外債務など財務リスクの有無や、適切に税金が支払われているかを調査します。
場合によっては、システム統合にかかる費用やライバル企業の動向、人材の価値に関する調査も並行して行われます。
多くの場合は買い手によって売り手の調査が行われてますが、M&Aにかかる交渉を円滑に進める為に、売り手自身が調査を行い、買い手に資料を提出する場合もあります。
デューデリジェンスについては、こちらの記事に詳しく説明してあります。
M&A必須過程!デューデリジェンス(DD)の意味や内容を解説します!
(3)ファイナンシャル・アドバイザリー業務(FA業務)
FA業務とは、財務に関する専門的な助言を行う業務のことです。
M&Aにおいては、交渉先企業の選定から契約成立に至るまでのM&Aに関連する一連の業務プロセス全体のアドバイスを行うことを指します。
M&Aのプロセスを一貫して頼めるので、複数の専門家に相談する必要がなくM&A成立までの手間を減らすことができます。
全ての税理士(事務所)が、M&AのFA業務に対応しているとは限らないので、事前の確認が必要になります。
近年は、M&Aに関連する業務に精通した複数分野の専門家を抱えたM&A仲介業者もあります。
3.M&Aにおける税理士の必要性

ここまでは、M&Aにおいて税理士が果たす役割について紹介してきました。
実はM&Aには、税理士必ずしも必要、というわけではなく、税理士を通さずに行われるケースが皆無というわけではありません。
ところが、売り手側としても、買い手側としても、M&A手続に税理士を介在させることによって得られるメリットはいくつもあります。
以下からは、税理士に依頼する必要性・メリットを具体的に解説していきます!
(1)節税対策
M&Aで会社や事業を売却する場合、帳簿上は譲渡価格が売り上げとなりますので、利益に応じた税金を支払わなければなりません。
当然、M&Aの規模が大きくなるほど売り上げは大きくなり、税金の支払い額も大きくなります。
M&Aが株式譲渡によって行われる場合、株主が個人の場合(創業者が自社株を売却する場合など)、株式の譲渡所得に対して所得税・住民税がかかります。
また、株主が法人の場合(事業の一部を譲渡する場合など)、株式の譲渡益は、他の所得と合算され、法人税などがかかります。
税理士は日常業務として、税務相談や税務代理を行っていますので、節税できるポイント等を熟知しています。
例えば、M&Aの際に退任する役員の退職金を差し引きして、所得として計算される金額を減らすといった方法がありますが、こうした節税ポイントやその実行は、税理士でなければ適切に処理することができません。
税理士に相談してM&Aを進めることにより、節税対策を行い、必要以上のコスト(税金)をかけずに手続きを進めていくことが可能になります。
②税務のリスクヘッジ
M&Aの税務処理は、経営者であっても何度も経験する事ではありませんし、M&Aをした年の確定申告は例年より複雑なものとなります。
そしてほとんどの場合で、税額は例年を上回るものになります。
そのため、正しい知識で節税を行わなければ、M&Aによる節税効果を得るつもりが、意図せず脱税になってしまうケースさえあります。
その場合、ペナルティとして追徴金を課される可能性もありますし、納税を怠ったことで信用を失い、会社の売上が大きく落ちる可能性もあります。
この点、税務の専門家である税理士のサポートがあれば、上記のような事態は防ぐことができます。
M&Aに精通する税理士であれば、より効果的な節税方法を提案してくれることでしょう。
(3)高品質のデューデリジェンス
税理士の役割でも述べましたが、財務・税務デューデリジェンスはM&Aにおける重要なステップです。
M&Aには多くのリスクが潜んでいますが、簿外債務・偶発債務・資産の価値低下・過去の納税状況などは、会計や税務の高度な知識がなければ見つけ出すことができません。
そこで税理士に調査を依頼する事によって、デューデリジェンスにおいてリスクとなる要因を見つけ出し、排除する事が可能になります。
交渉を進める上でも、税理士が行うデューデリジェンスによるリスクヘッジは有利に働きます。
なぜなら、税務・財務に関する調査のレベルが高いと、デューデリジェンスをする買い手側もデューデリジェンスを受ける売り手側も安心して対応を任せることができるからです。
税理士によるデューデリジェンスを通して、本当に信頼できる相手かどうかを知ることもできます。
相手企業の債務や売上、会計の実態を正しく把握することで、M&A手続きがスムーズに進みます。
(4)適正な価格の算出
税理士にバリュエーションを依頼することにより、M&Aにおける適正な売買価格を算出する事が可能になります。
客観的なデータに基づく専門的な判断は、売り手側にも買い手側にも有益なものとなります。
売り手側のメリットは、自社の価値を最大限まで伸ばすバリュエーション手法の活用により、見込める売買金額の最大値がわかる事です。
それは買収価格の交渉において目安となり、自社の価値を無駄にすることなく交渉を進める為の材料となります。
一方買い手側のメリットは、減損によるM&A失敗のリスクを軽減することができる事です。
買収価格が、本来の価値以上に高額になってしまうと、将来的に減損などの深刻な損失を被るおそれがあります。
税理士のバリュエーションにより、買収対象企業の本来の価値を知ることで、必要以上のコストをかけずに済み、将来的な減損などのリスクを減らす事にもつながります。
(5)M&Aに有利なネットワーク
M&Aには、法務や経営など様々な分野の専門家によるサポートが必要です。
とはいえ、すべての専門家がM&Aに精通しているというわけではなく、むしろ全くM&A業務を経験したことがないという場合がほとんどです。
この点、M&Aを得意とする(実績のある)税理士の中には、M&Aに詳しい他分野での専門家とのネットワークを持っている事があります。
実績のある税理士にM&A実務を請け負ってもらえば、弁護士や公認会計士などの他分野の専門家を紹介してもらえる可能性が高いです。
その場合、専門家同士の連携も取りやすく、よりスムーズにM&A続きを進めることができます。
4.税理士費用の相場

M&Aにおける税理士の必要性について、ご理解いただけたでしょうか?
では、実際に税理士にM&Aに関する業務を依頼すると、どれほどの費用がかかるのでしょうか。
結論からいうと、費用はピンキリであり、M&Aの規模や依頼する内容、所属事務所によって大きく異なります。
今回は、おおよその相場を見ていきますので参考にしてください。
また、後々のトラブル防止の為にも、事前に予算を伝えておく事や相見積もりを行うことをおすすめします。
(1)バリュエーション
対象企業の規模にもよりますが、およそ30~50万円ほど必要になります。
企業が大きくなれば業務が複雑化する為、それに伴い金額を大きくなります。
ベンチャーやスタートアップであれば、100万円を超えるケースはほとんどありません。
(2)デューデリジェンス
こちらもバリュエーションと同様に企業規模により異なりますが、30~50万円ほどが相場になります。
規模だけでなく、業種や事業所数によっても異なりますので、事前の相談をおすすめします。
下記に述べるFA業務のような一括委託ではない単発の依頼としては、最も費用がかさむ業務ではあります。
(3)ファイナンシャル・アドバイザリー(FA)
FA業務はM&A手続きを一貫して請け負う為、費用は100万円ほどかかります。
様々な手続きが含まれている業務であるため、高額になりやすい傾向があります。
企業の規模によっては数百万円から数千万円になるケースもあるので、事前に必ず見積もりを行うようにしましょう。
また、売買金額によって報酬金額が決まるレーマン方式を採用している税理士(事務所)もあります。
成功報酬型を採用している場合は、M&A成立時の支払いなので資金の圧迫を抑えることができます。
5.M&Aに強い税理士を探す方法

最後に、実際に税理士を依頼する際のポイントについて紹介します。
税理士に依頼する際に最も注意すべきなのは、税理士であれば誰でも良いという訳ではないということです。
おそらく、ほとんどの企業では既に顧問税理士がいたり、税務処理の際に決まって依頼している事務所があると思います。
しかし、全ての税理士が、M&Aに関しての知識を備えているわけではなく、身近な税理士が必ずしもM&A手続きの力になってくれるとは限りません。
ここまでM&Aにおける税理士の役割についていくつも述べてきましたが、M&Aに関する知識が豊富な税理士に依頼しないと、これまで述べたようなメリットは得られません。
M&Aに精通した税理士は手続きがスムーズなだけでなく、リスクヘッジ等においても頼りになる存在ですので、慎重に選ぶ必要があります。
最近ではインターネットでも探すことができ、その際は費用に関しても確認する事ができますので、参考になるでしょう。
M&Aに強い税理士や弁護士などを探せずにお困りの方は、以下のお問い合わせフォームからご連絡ください!
6.まとめ
M&Aにおける税理士の役割と依頼するメリット・必要性の解説は以上になります。
財務・税務手続きは、その複雑さゆえに正確性が求められます。
専門知識だけでなく、経験がないと思わぬトラブルを引き寄せてしまいます。
M&Aの際、双方当事者としては、いかに自己にとって有益な目的を達成するかに主眼が置かれるため、手続き自体に気を配る余裕を持つことは現実的に難しいです。
安心して手続きを任せられる専門家がいると、本来経営者が考えるべき問題についてしっかり検討する事ができます。
M&Aは様々な専門家に相談する事が推奨されていますが、ぜひ税理士にも相談してみてはいかがでしょうか。
実績のある税理士の協力は、M&Aをより満足度の高いものとしてくれることでしょう。
今回はM&Aにおける税理士の役割について紹介しましたが、弁護士の役割については以下の記事を参照してみてください。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。