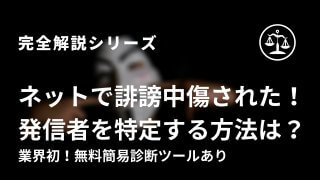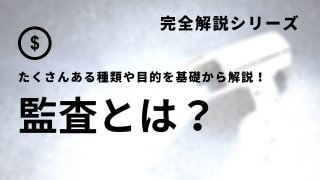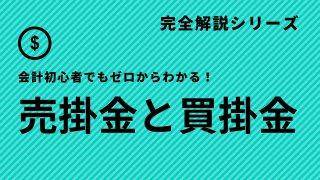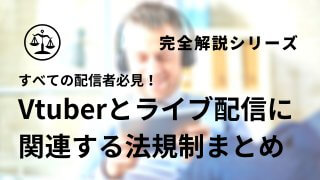0.事案の概要
この事案は、校長にパワハラを受け続けていた、とする小学校教員Xが、うつ病に罹患し、休業し、精神的苦痛を受けたことの賠償を、甲府市と山梨県(あわせてY)に対して請求した事案で、裁判所はその一部について責任を認めました。
1.判断枠組み(ルール)
裁判所は、パワハラの定義として、いわゆる「いじめ円卓会議」で示された、以下の定義を用いています。改正法では、パワハラの定義が明確化されましたが、ここでは裁判所の判断に関する以下の定義に関し、検討します。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性(※)を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。(※上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。)
具体的には、この定義に該当する場合であっても、それが「業務上の指導者として社会通念上許容される範囲を超えていたか、相手方の人格の尊厳を否定するようなものであった(か)等を考慮して判断する」と、その判断枠組みを示しています。つまり、①パワハラの定義に該当するかどうか、②それが許容される範囲を超え、人格の尊厳を否定するかどうか(許容範囲等)、という2つの視点から判断する枠組みである、と整理できます。
けれども、この中で、①については、Xが好調によるハラスメントと指摘する20近い行為を1つひとつ吟味する中で、裁判所が①の該当性についての判断を示さず、「パワハラに該当するかはともかく」と述べている個所がいくつかあります。他方、結論として「パワハラに該当しない」と述べている個所も多くあります。
さらに、定義の中の「業務の適正な範囲を超えて」という表現と、②の関係も明確ではありません。
このことから考えると、判断枠組み自体は厳密に整理されていないものの、①外見的にパワハラに該当する行為があったかどうか、という問題と、②具体的にそれが違法な程度かどうか、という問題に分けて整理している、と理解するのが良さそうです。
枠組みはこのように整理するとして、いわゆるパワハラ6類型について、簡単に触れておきます。
これは、法改正に先立ついわゆる「いじめ円卓会議」で示されたパワハラの類型です(a 身体的な攻撃、b 精神的な攻撃、c 人間関係からの切り離し、d 過大な要求、e 過小な要求、f 個の侵害)。円卓会議や今回の法改正の検討過程で、この6類型に該当するかどうかの検討が重要、とされており、実際、ハラスメント該当性を検討する際、どの類型に該当するか、という観点から検討すべきである、と指摘する論考も見受けられます。
けれども、このパワハラ6類型は、上記①の判断にとって有益ではないか、とも思われますが、この裁判例では、同じ「いじめ円卓会議」で示された、パワハラの定義は引用するものの、パワハラ6類型に言及すらされていません。
パワハラ6類型は、ハラスメント該当性の判断にとって不可欠なものではない(議論を整理するうえで有益かもしれないが)、と言えるでしょう。
2.パワハラの認定(あてはめ①)
次に、パワハラの認定に関する特徴です。
この事案は、普段の業務指導での校長の言動については、その全てがパワハラでないと認定されているのに対し、Xが訪問先の児童の家で犬に咬まれたこと(犬咬み事故)によって生じた児童の家庭とのトラブル後の校長の言動については、かなりの部分でパワハラと認定されています。このように、犬咬み事故の前後で校長の言動の評価が真逆になったことが、重要なポイントになります。
そこでまず、前半部分について検討しましょう。
前半部分でのXの主張は、H24の4/1に着任した校長が、4/6の新任教員歓迎会に向かう車内でXらを恫喝した、4/9の職員朝礼でXの発言について全員の前で叱責した、4/11の朝の打合せでXを叱責した、などというもので、Xがパワハラと主張する行為は14にものぼります。
しかし、裁判所はこの全てについて、①パワハラに該当しないか、②それはともかくとして許容範囲等を逸脱していないとして、校長やYの責任を否定しています。
ここでの事実認定の特徴の1つ目は、認定方法です。
特に録音がある様子もなく、多くの言動がXと校長の証言だけが証拠である、という状況です。単に、対立する当事者の対立する証言しかないのであれば、真偽不明である、として立証責任の問題で処理しても良さそうです。そしてもしそうなれば、賠償責任を請求するXが立証責任を負いますので、真偽不明であることの不利益はXが負うことになり、すなわちXの請求が否定されることになります。
けれども、結果的にはそうであっても、裁判所は地方公務員災害補償基金による聞き込みなどの調査資料で明らかとされる、Xの同僚の証言や感想を突き合わせ、それすらない場合にはお互いの証言を突き合わせて、どちらの証言の方が合理的かを検討しています。さらにそれでもはっきりしない場合には、「しかし、そのような発言があったとしても、それがパワハラに該当するかはさておき、…不法行為を構成するとはいえない。」等と判示し、上記②の部分でXの請求を否定しています。
裁判所は、証言が食い違えば証明不能で原告の負け、と簡単に処理するのではなく、他の手続きでの資料や、それが無ければ証言自体の合理性、さらにそれすら無ければ仮に原告主張のとおりだとしてどうなるのか、という3段階の工夫を重ねて、立証責任による解決を回避しています。
したがって、実務上のポイントとして、この事案ではYに軍配が上がりましたが、お互いに証言が無いなら会社の勝ちだ、と言うほど簡単ではないことに留意することを、指摘できるのです。
2つ目は、「過敏な被害者」です。
これは、セクハラの裁判例が出始めたころの議論です。一方で、アメリカの犯罪心理学の研究成果(強姦被害者は、心身のダメージを減らすために、犯罪者に迎合的な言動を取る傾向が強く、表面的に同意するような言動が見えても、それを真の同意と評価できない、とする研究結果)から、被害者の同意を否定する(したがってハラスメントを認定する)裁判例が出された一方で、客観的に見れば到底セクハラに該当しないし、加害者とされる人物もそのような意図が全く無いのに、自分は被害者だと過剰に反応する「過敏な被害者」が存在する、その場合には被害者の申告を慎重に見極めなければならない、という見解を示した裁判例が出されました。
結局、このどちらが正しい、という話ではなくて、事案ごとにXの人柄や状況を踏まえて個別に判断する問題ということで、最近は「過敏な被害者」という言葉を見かけなくなりました。
しかし、この事案でのXの主張とそれに対する裁判所の判断を見ていると、例えば、4/6の車内での会話は、新任の校長が、教育委員会との付き合い方などの一般的な話をしていただけ、と認定し、4/9の職員朝礼での発言は、4/6の車内でのXの発言に対する嫌みを言っているのではなく、一般的な作法を話したに過ぎない、と認定するなど、Xを「過敏な被害者」と同様に位置付けているようにも見えるのです。
3つ目は、Xの認識です。
Xがどのように考えて、パワハラと主張しているのかはわかりませんが、その主張の背景には、ハラスメントは被害者がハラスメントと感じればハラスメントとなる、という、いわゆる「主観説」が見て取れます。
たしかに、精神的損害は被害者の精神的苦痛が無ければ発生せず、したがって被害者の精神的苦痛の存在が不法行為成立の要件の1つとなります。
けれども、そのような苦痛を与えた行為が違法であるかどうか、という問題については、被害者がどう思うかという問題ではなく、社会一般が違法と評価するかどうか、という問題です。この意味で、違法性の問題について言えば、「主観説」ではなく「客観説」です。Xの主張を突き詰めると、自分が恫喝されたと感じたから違法である、自分に対する嫌みを多くの人の前で言われたと感じたから違法である、ということになりますが、これは「客観説」であるべき損害賠償の請求として、不適切であり、客観的な違法性の主張が欠落している点で、不十分なのです。
3.モンスターペアレントへの対応(あてはめ②)
これと打って変わって、犬咬み事故後は、校長の言動のほとんどがパワハラと認定されています。
ここで特に注目されるのは、いわゆるモンスターペアレントとも言うべき苦情をXが受けている状況での、校長の対応です。
すなわち、児童宅を訪問したXが、そこの犬に咬まれた際、Xの怪我に対する補償の問題に触れたところ、児童の父と祖父が、「地域の人に教師が損害賠償を求めるとは何事か」「強い言葉を娘(生徒の母)に言ったことを謝ってほしい」などとして謝罪を求めてきたのです。言わば逆切れであり、教師をまるで奴隷扱いするような前時代的な発想ですが、校長はXに対し、この父と祖父に対して謝罪することを命じました。
これに対して裁判所は、児童の両親が法的責任を負うのが当然の事故であって、「権利の行使として何ら非難されるべきことではない」のに、「泣き寝入り」させた評価しました。さらに、「校長は、本件児童の父と祖父の理不尽な要求に対し、事実関係を冷静に判断して的確に対応することなく、その勢いに押され、専らその場を穏便に収めるために安易に行動したというほかない」と厳しく評価し、不法行為の成立を認めました。
この判断から読み取れることは、モンスターペアレントによる理不尽な要求があった場合、上司である校長は、①部下であるXに権利放棄させるなどはもってのほかで、②安易な解決をするのではなく、少なくともXの権利行使の機会を奪わないように対応しなければならない、と言えます。②について、校長が実際に何をすべきなのかは何も語られていませんが、Xが権利行使できるようにする、ということは、当然、この父と祖父の苦情が継続し、エスカレートすることが想定されますから、Xが苦情を受けても教師としての業務を遂行できるようにする必要があります。そうすると、X自身が苦情対応すると、苦情がエスカレートした場合には授業どころでなくなってしまいますから、そうならないようなサポートをすることも、校長の義務になると言えるでしょう。
モンスターペアレントの問題は、カスタマーハラスメントの問題とも重なります。組織の業務の相手方からの攻撃という点、攻撃にさらされる担当者を上司や組織がどこまでサポートすべきかという点、について共通する状況があるからです。
先例が少ない中で、モンスターペアレントからの苦情対応で上司や組織の責任を認めた事案として、今後、非常に参考になる示唆を含んでいるのです。
4.実務上のポイント
最後に、今回の法改正によってパワハラの定義が法律上明確になったことの影響を考えてみましょう。
今回、労働施策総合推進法に追加された30条の2では、以下のように事業主(会社)の責任を定めており、この中の下線部分が今後のパワハラの定義となります。
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
ここで示された定義からパワハラの要件が見えてきますが、①優越性、②必要性・相当性の逸脱、③就業環境の侵害、の3つに整理するとわかりやすいでしょう。そのうえで、これを上記「いじめ円卓会議」の定義と比較すると、言葉の意味がより分かりやすくなります。
すなわち、①は、「優位性」から「優越性」に変更されました。
立法過程での議論では、「優位性」の場合には上司と部下のように、上と下の関係を意味するが、「優越性」の場合には、部下が徒党を組んで上司をいじめる場合のように、人事上の上下関係に限定されず、その範囲が広がっています。
すると、会社外の人間からのハラスメント(モンスタークレイマーや上記のモンスターペアレント)についても、例えば顧客や取引先には「優越性」があるのではないか、したがってパワハラに該当するのではないか、という議論が可能です。「職場において行われる」という言葉が「言動」に係っており、(職場での)「関係」のような表現になっていないことも、この解釈を可能にするように思われます。
しかし、会社が従業員を顧客や取引先から守る義務があることを、一般論として認めることができるとしても、具体的にどのような状況になれば会社の責任となるのか、という問題については、会社の側も顧客や取引先を簡単にコントロールできませんので、どのような事情を考慮して、どこに線を引くのか、という問題を簡単に解決できません。
顧客や取引先からのハラスメントについては、この文言の解釈問題と具体的な認定の問題が密接に絡む問題として、今後議論されることと思われます。
このように見れば、①の変更は、パワハラの範囲に関する議論(カスハラやモンスターペアレントの問題など)を活発にする可能性があります。しかし、賠償責任の認定や責任の範囲、程度などに関する影響は、少なくとも従前から議論されている典型的なパワハラ事案については、小さいと言えるでしょう。
次に、②は、「業務の適正な範囲を超えて」から「業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより」に変更されました。
さらに言えば、ここには、この裁判例が「業務上の指導者として社会通念上許容される範囲を超えていたか、相手方の人格の尊厳を否定するようなものであった(か)等を考慮して判断する」と示している部分も含まれると評価できそうです。
しかし、この変更は、例えばパワハラの範囲が変るなどの重大な影響はないように思われます。むしろ、ハラスメントとされる行為が、業務上「必要」だったか、それが常識的に「相当」だったか、という形で議論を整理する場合がありました。この必要性と相当性は、社会的相当性を判断する際の整理方法として他の法領域で活用される場合があり、それをパワハラ認定の場面で応用する発想です。まず、その行為自体の問題(必要性)を検討し、次に、その行為以外の事情との関係性(相当性)を検討する、という整理であり、今後、議論の整理に貢献することが期待されます。
このように見れば、②の変更は、議論の整理に役立つかもしれないが、特に責任の範囲が変わるとは思われないことから、その影響は小さい、と言えるでしょう。
次に、③は、「精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる」から、「就業環境が害される」に変更されました。
この文言の違いだけを見ると、会社は従業員に対し、パワハラによって「精神的・身体的苦痛を与える」ことのないように配慮する義務がない、したがって本件事案のようなパワハラの責任を負わない、という解釈ができそうです。
けれども、この変更は、今回の法律が事業主(会社)の公的な立場(義務)に関する規定であり、個別の紛争への対応を想定していないから、という評価も可能です。つまり、個別事案での私人間の損害賠償の問題に関するルールを定めるべき条文ではない(会社の公的な義務などに関するルールだから)、環境整備だけでは避けられない紛争が生じてしまった場合に、それを予見したり回避したりする義務(=過失責任)があったかどうかという問題は、今回の法律が関知しない問題であり、従前の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償のルール(特に判例など)が適用されるのであって、これを積極的に排斥しない(従前のまま有効に存続する)、と解釈される可能性の方が大きいと思われます。
このように見れば、③の変更の影響は小さい、と言えるでしょう。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、毎週、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。