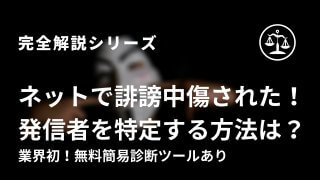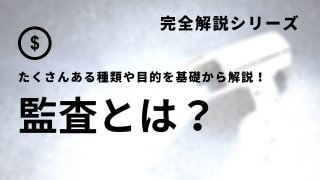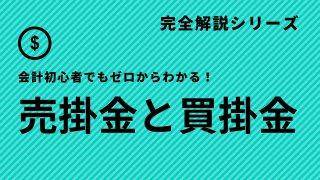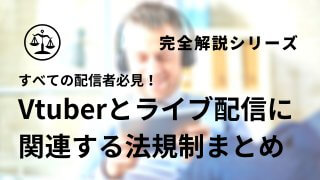0.事案の概要
この事案は、育休を取ったことによってさまざまな不利益処分を受けた、と主張する大学講師Xが、大学Yに対して損害賠償を請求した事案です。裁判所は、その請求の一部を認めました。
1.定期昇給
そのうちの1つが定期昇給を受けられなかった点です。すなわち、給与規程上、1年間のうち一部でも育休を取得すると定時昇給が受けられなくなる、という規定の合理性です。
この点、裁判所は、①定期昇給を、勤務年数に応じて自動的に計算される「年功賃金的」なものと見れば、この趣旨に反する、②定期昇給を、職務経験の蓄積に応じて定める「職務能力給的」なものと見ても、勤務した期間の職務能力の向上を一切否定することになり、合理性がない、として、育休法10条の「不利益な取扱い」に該当すると評価しました。
2.減年調整
つぎに、減年調整を一部されなかった点です。
この減年調整は、独特な制度なので少し説明が必要です。
まず、減年制度です。
これは、中途採用する職員について、前職の勤務経験年数を、採用後の職種とどこまで類似しているのか、という性質に応じて換算し、一定割合減少させる制度です。実際、Xは、高校教諭等を務めていた11年7か月については60%(6年11.4か月)、その余の6年5か月については100%(6年5か月)として、合計13年4.4か月を、大学卒業時の基準年齢22歳に加算し、「本俸表」の適用年齢が35歳になることを前提に、年俸が決定されました(Xは、この換算方法を違法として訴訟しましたが、敗訴し、控訴・上告後、敗訴が確定しています)。
次に、減年調整です。
これは、一定年度勤務している中で、上記減年分を少しずつ取り戻していく調整です。その内容や基準は公開されておらず、裁判所も、減年調整にはY側に相当の裁量がある、と判断しました。しかも、育休取得者には、他の従業員の減年調整の半分の調整を行うこととしており、育休取得者に対する相当の配慮をしている、と評価しました。
3.増担手当
次に、増担手当の返還を求められた点です。
これは、基準を超える時間の授業を担当した場合の「増担手当」について、育休を取ったために、年間通じて計算すると「増担手当」支給条件が満たされなくなったとして、その返還をYがXに対して請求したことについて、Xが不法行為の成立を主張したものです。
結論的には、Xは実際にこれをYに返還したわけではなく、損害がない、などの理由で請求を否定していますが、年間通じて計算する、という方法について、裁判所は合理性を否定しました。
4.問題の所在
以上の3つの問題点の検討から、共通する問題点は、育休法の「不利益な取扱い」の評価基準です。
枠組みとしては、①法律は休みを与えることだけしか要求しておらず、それを無給の「欠勤」として扱っても違法ではないけれども、②育休に伴うそれぞれの措置が、従業員の権利や法的利益の趣旨を実質的に失わせる場合には、公序良俗違反により無効になる、と言われています。
ここでは、このうちの②について、3つの実例が示されたと言えるでしょう。すなわち、定期昇給と増担手当については、「不利益な取扱い」に該当するが、減年調整については、「不利益な取扱い」に該当しない、と評価したのです。
この判決の中では、主にYの裁量の有無が判断の分かれ目になっているようです。
しかし、いずれも特殊な手当てについての判断であり、ここでの判断、すなわち会社側の裁量の有無が判断の分かれ目になるかどうかについては、今後の裁判例などを通して具体的に明らかにされていくべき問題のように思われます。
5.実務上のポイント
この裁判例が掲載された労判1202(2019年8月1日15日合併号)の巻頭言「遊筆」で、上智大学名誉教授の山口浩一郎先生執筆の「不自然な『過失』と労契法20条」という原稿が掲載されています。
ここでは、労契法20条に関し、違法状態について過失がある、過失がない、という議論を最近の判決の中で見かけるが、このような議論は不自然ではないか、労契法20条本来の役割から見直すべきではないか、という趣旨の指摘がされています。
他方、ここで検討した判決では、労契法20条ではなく、会社の給与規程等が育休法の規定に違反するかどうかについて、上記1の定期昇給については、給与規程の違法性について、過失があった、と認定していますが、反対に、上記3の増担手当について、過失がなかった、と認定しています。
かつては、「法の不知は保護せず」という有名な法格言が適用されると言われていたので、違法状態についての過失、という概念は存在しないはずでした。
けれども、例えば刑法では、「違法性の意識」(例えば、(人の物を盗むのは)悪いことだ、という意識)について、有罪と認定し犯罪者を処罰するためには、犯罪者自身の違法性の意識が必要かどうか、という問題が古くから議論されています。詳細は省略しますが、裁判所は「違法性の意識」そのものは不要だが、「違法性の意識」の可能性は必要としている、と言われることがあります(団藤・前田)。
この「違法性の意識」の問題は、刑法の中では「責任論」に位置付けられており、民法不法行為法の「過失」の判断とは位置付けが異なりますが、しかし両社は非常に似た問題意識に基づく議論です。
特に、労契法20条や育休法など、法制度やルールの変化が激しい領域では、会社側従業員側双方にとって、新しいルールに基づいた場合、それが違法なのかそうでないのか、アップデートするのが難しい領域が増えています。しかも、ここで見たように、機械的に当てはめて結論が出る問題ではなく、結局、裁判になってみないとわからないような曖昧な問題も増えています。
そうすると、今後は、「違法性の意識」の可能性と同様、会社の就業規則の規定や、会社の運用が、違法であることについて過失があったかどうか、が議論の対象になる場面が増加していくでしょう。
これを会社の人事の側から見た場合、新しく制定されたルールが「不利益な取扱い」などの曖昧な基準(規範的な要件)であり、それに自社の就業規則などが違反するかどうか曖昧で判らない場合には、専門家の弁護士に鑑定してもらい、違法である可能性が小さいことを確認するなどの事前対応を尽くしておくことによって、「過失」認定される危険を減らすことが期待できます。
今後のコンプライアンス対応のポイントとして、非常に注目されるポイントですので、ぜひ、活用してください。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。