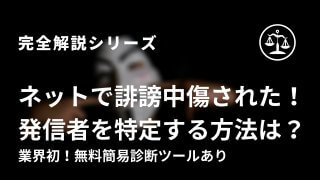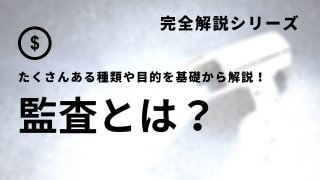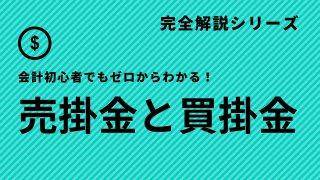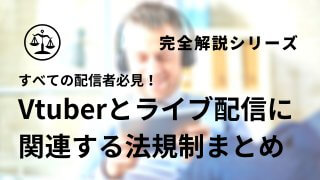0.事案の概要
この事案は、育児のために時短を求めた女性従業員X(無期契約)に対し、会社Yが、時短勤務のためにはパートでなければならないとしてパート契約(有期契約)への変更に合意させ、その後、有期契約の更新を拒絶した事案です。裁判所は、これに対し、パート契約の変更に合意させた点が育休法に違反するとして無効とし、Xが無期契約社員であると判断しました。
1.育休法23条の2
裁判所は、育休法23条の2に反する措置は無効である、としたうえで、「自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する」場合であればこれに該当しないが、Xについてはこのような場合に該当しないとして、有期契約への変更を無効としました。同条の「解雇その他不利益な取扱い」に、このような「自由な意思」のある場合は含まれないのです。
この、「自由な意思」「合理的な理由」「客観的に存在」は、山梨県民信用組合事件に示されたもので、最近の数多くの裁判例で採用されている基準です。詳細な検討は省略しますが、通常の意思表示の場合よりも、有効と認められる基準が高くなっており、民法総則に定められた意思表示のルールが、労働法分野で大幅に修正された状況です。
問題は、この「自由な意思」基準が適用される対象の範囲です。
これまでのところ、どうやら強行法によって労働者が保護されている領域に関して適用されているように思われます。これは、強行法の意味から考えると、理解しやすいでしょう。すなわち、強行法であるということは、労働者が合意していても、その合意を無効にしてまで労働者を保護する、ということを意味します。そうすると、合意に反しても労働者を守ろうとするルールについて、労働者がそのような保護は不要である、と言えるためには、使用者側の説明を十分理解し、特にその不利益も甘んじて受け入れることの意思が十分担保されない限り、強行法の脱法行為になってしまいます。
このことから、強行法による保護すら不要、と評価するに値するだけの合理性を担保するために、「自由な意思」「合理的な理由」「客観的に存在」が必要となるのです。
このように見ると、育休法23条の2を強行法であると評価した裁判所が、「自由な意思」基準を適用したことには、一貫性があるように思われるのです。
2.実務上のポイント
2点、補足説明をします。
1つ目は、「自由な意思」基準の適用範囲です。
強行法に反する意思表示の場合に適用される、という整理が、理論的に納得しやすいようですが、数多くの下級審判例の中には、必ずしも強行法違反ではない事案で、「自由な意思」基準を適用しているものがあるかもしれません。
現時点では、強行法に反する場合が適用範囲である、というのは、1つの仮説にすぎない、と考えておくのが無難です。
2つ目は、裁判所の表現です。
労判の当該箇所の解説では、裁判所の表現に「一定の不明確性が残されている」という評価を与えています。この解説は、この裁判所は、「解雇その他不利益な取扱い」には一方的な行為しか含まれないとしており、その上で、合意に基づく場合には「自由な意思」基準が適用される、としているが、一方で、「自由な意思」が「解雇その他不利益な取扱い」該当性の問題と読める表現も用いている、という「読み方」を前提にしています。
けれども、この裁判所は、「解雇その他不利益な取扱い」には一方的な行為しか含まれないと説いていません。曖昧かもしれませんが、この「解雇その他不利益な取扱い」について、法文の表現をそのまま引用しているだけで、その意味を特定するような解釈を示していません。
他方、合意に基づく場合には「直ちに違法、無効であるとはいえない。」という表現をしており、合意に基づくことは、育休法24条の2適用の要件としてではなく、適用を排除すべき抗弁として位置付けています。続けて、この「合意」について「自由な意思」基準が適用される、と論じています。
つまり、育休法24条の2には、正社員からパート社員に契約変更する場合なども含まれ、原則として無効だが、それが「自由な意思」基準に合致する場合には、例外的に有効となる、と評価されるのです。
もっとも、この2つ目の問題は、実は重要ではありません。
例えば、解雇権濫用の法理です。
現在でこそ労働契約法17条で、合理的な事情の存在を会社側が証明しなければならないことが、条文の文言と文法上、明確になりましたが、かつては、解雇は原則自由で、濫用に該当する場合は解雇できない、と説明されていました。この説明だと、合理性を争う従業員側が立証責任を負うように見えるのですが、実際は、解雇の合理性を会社が説明できなければ会社側が敗訴する、という運用が定着していました。
したがって、会社側の判断の合理性が強く求められる場面では、立証責任の問題の重要性は低下してきており、「自由な意思」基準の適用について、仮に従業員側が立証責任を負うとなっても、同様に、実際は会社側が合理性を証明できなければならないことになるでしょう。
この意味で、2つ目の問題は、それほど重要な問題とは思われないのです。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。