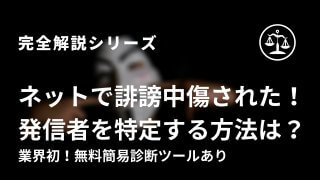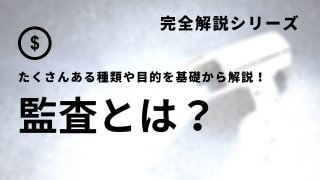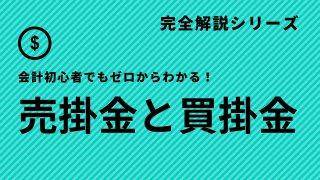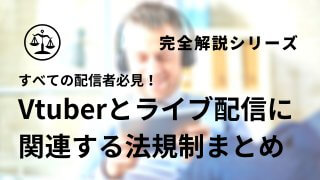0.事案の概要
この事案は、当連載2019/1/29(労判1188.5、「参考裁判例」)と同じ事案に関し、異なる原告に対して示された判断です。参考裁判例と同様、従業員であると主張する原告Xの請求を否定しています。
この裁判例も、参考判例も、共に商法14条の適用などが問題になりましたが、この点についてはここでの検討を省略します。ここでは、本来の争点である「従業員性」(≒「商業使用人」該当性)について検討しましょう。なぜなら、会社経営者が雇用者としての負担を避けるために、実質的には従業員であるにもかかわらず、雇用契約ではない法律構成での契約を締結し、そのことで実質的には従業員が過度な不利益を被る事例が、かねてより数多く見受けられ、「従業員性」は重要な論点となっているからです。
1.従業員性
参考裁判例の解説では、従業員性のないことが比較的明らか、とコメントしましたが、従業員性が正面から争われた本裁判例を読むと、それほど簡単ではないことがわかってきました。このことは、「従業員性」の根拠として指摘するポイントと、それに対する裁判所の評価を対比するだけでもイメージが伝わりますので、項目のタイトルにXの主張、本文に裁判所のコメントを記載する方法で、箇条書きに対比します(項目番号は、裁判例の項目番号に合わせています)。
詳細に読まなくても、眺めるだけで構いません。
ア Yに、契約解除権限、監査権限、業務改善命令の発令権限があり、Xは仕事を選べない。
代理店が仕事を自由に選べないこと、契約当事者が契約を解除できること、全国展開するうえで一定の統制が必要であること。
イ 営業地域をYに強制された。
Xは同意しており、強制されていない。
ウ Yは、代理店長を異なる地域の支部長に選任したり、Xを70歳定年を理由に解任した。
支部長は同意したのであって、Yの人事権はない。解任は、Xが同意したのであって、定年はない。
エ Xの業務内容について、Yが指揮命令していた。
Xが、代理店契約に基づいて行うべき業務だった。
オ Xは、相当時間拘束されていたので、指揮命令があった。
代理店契約上、拘束時間の規定がない。Yは勤務時間を指示していない。
カ Xは、営業目標達成を強制されていたので、指揮命令があった。
委託者として営業目標達成を指示することは当然。
キ Yへの稟議が必要なイベントを義務付けられたので、指揮命令があった。
Yは義務付けていない。稟議も、費用負担の要請だけであって、開催自体の稟議ではない。
ク Xの採用活動を、Yが指示していた。
最終的にはXが採否を決していて、Yは直接決定していない。稟議も、費用負担の要請だけであって、採否の判断自体の稟議ではない。
ケ YがXの従業員の給与を直接支払っていたので、指揮命令があった。
振込はYがしていたが、これは代理店契約に基づくもので、Xのすべきことの代行にすぎない。
コ YがXの従業員の労働条件を指図し、管理していた。配置換え、懲戒、解雇などの決定権あった。
代理店と従業員の間の雇用契約の内容は、基本給を含めて統一されておらず、Yには雇用条件の決定権限がない。タイムカードなどの資料提出や担当者コードを割り付けていても、実際に労務管理していない。Yが配置換え、懲戒、解雇した証拠はない。XがYの求めどおり、従業員の給与を18万円とし、3か月以上欠勤した従業員を解雇したことがあるが、これもXが判断したこと。
サ Yは、研修受講指示、担当換え、業務上の命令・指示、をした。
たしかに、代理店のFAに対する指示が一定程度あった。
しかし、指示はX経由。これらの制約は代理店契約に由来する。目標未達でも担当外されない例もある。保険事業について、直接担当者に文書が送られたことがあっても、直接指示命令はない。
シ Xは拠点となる事務所を自由に決定できず、場所的な拘束を受けていた。
たしかに、費用はX負担だが、事務所はYが借りてXに使用させることになっていた。
しかし、Yの定める事務所を借りる義務はない。Yは賃料の差額を負担してXを経済的に支援しており、代理店支援策である。
ス 代理店の報酬は、Xの労務の対価である。
たしかに、報酬は経費を控除したうえで給与の名目で振り込まれていた。
しかし、これにはXの従業員の報酬も含まれているので、Xの労務の対価ではない。
セ 報酬額はYの指示で決まり(経費を下回ったときは貸付など)、請求書もYが原案を作成した。
報酬額は、代理店契約の定めにより機械的に定まったのであって、Yが決めていたのではない。貸付金処理は、Xの求めによる場合もあり、Yが一方的に決めた証拠はない。
ソ Yの指示でFAと費用が膨らみ、Xが報酬を決める裁量がなかった。
FAの採用や給与は代理店が決めていた。
タ 代理店契約の名義、Xの従業員の業務内容・労働条件決定者、売り上げの帰属がY
契約名義は重要でない、代理店契約に基づくX自身の業務のための採用、労働条件をYが決めていない(上記コ)、代理店契約だからビジネスの成果がYに直接帰属するのは当然。
チ 再委託が禁止されていて、代替性が無い。
従業員を多数雇っており、代替性がある。
ツ XがYの組織に組み込まれている。
たしかに、代理店がYの下部組織、名称も支部等、公的報告で従業員扱い、YがX従業員の報酬支払、労契上の肩書、支部が代理店従業員を引き継いだ。
しかし、Xの判断で従業員を採用するなど、独立しており、Yの専属ではなかった。名称や報告上の位置付けは形式面にすぎない。Yは、X従業員の報酬支払いを代行していたにすぎない。支部が引き継いだ従業員は自分の意思で転籍したのであって、Yの人事権による一方的なものでない。
2.実務上のポイント
ここで、Xの主張と裁判所の認定を羅列したのは、①上記各事実の中には、他の裁判例と比較すると、従業員性を肯定すべき事情となり得るものも見受けられること、②裁判所はそれらをバラバラにし、一つずつ単体で従業員性を認めるべきかどうかを問題にしていること、が読み取れるからです。
もちろん、裁判所の判断の冒頭部分で、総括としてXとYの関係を整理しているので、「木を見て森を見ない」というわけではありません。
しかし、例えばハラスメントの成否に関し、一つひとつの行為を見れば不合理とまで言えなくても、全体として見ればハラスメント、と認定する裁判例もあるように、従業員性についても、総括の部分について、一つひとつの事実の評価をまとめただけでない、総合的な評価が加わる可能性も否定できません。
従業員性を巡る訴訟は、会社側が制度や運用を改める度に訴訟が提起される事案もあるなど、長期化する場合が見受けられます。他方、会社が従業員を抱えることを避けようとする動きは、常に一定数存在するようで、そのために新たなスキームや契約形態が考案されます。このことから、従業員性の問題は、常に新しい論点が発生している領域であり、従業員性の概念自体が常にゆれ動いています。
このように見ると、従業員でない形態のスキームや契約形態は、一度トラブルになると、ビジネスモデル全体に長期的な影響を与えるリスクが有ることを認識して、慎重に検討する必要性のあることが、理解されるのです。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。