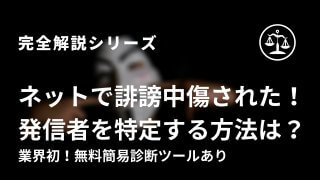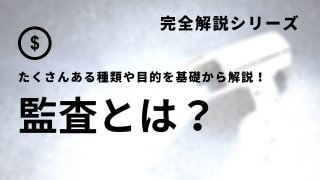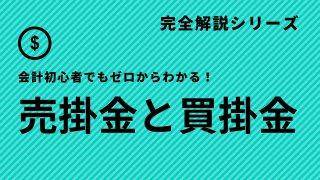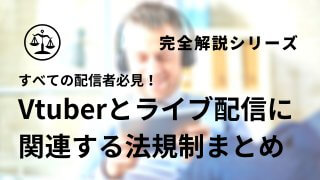0.事案の概要
この事案は、支店長やマネージャーとして割増賃金を支給されなかった従業員Xが、会社Yに対して、支店長やマネージャーは労基法41条2項の「管理監督者」に該当しない、したがって割増賃金が支払われなければならない、と争った事案です。裁判所は、Xの請求を認め、Yに対して割増賃金の支払いを命じました。
1.判断枠組み(ルール)
労契法41条2項の「管理監督者」に該当すれば、割増賃金が支給されなくなりますので、人件費を節約するために、いわゆる中間管理職者などを広く「管理監督者」と解釈し、割増賃金を支給しない会社が多く、裁判例も多く存在します。
裁判所は、「管理監督者」かどうかを評価するにあたり、①経営者との一体性、②労働時間の裁量性、③相応しい待遇、という3つの要素から評価することが多いようです。この事案も、この3つの要素で判断しています。
このうち、特に①について、経営者と一体ではなくても、会社の重要な組織や部門を統括する場合、これに該当するという趣旨の裁判例もあります。特に、この事案では、2審でYが、管理監督者は経営者の分身であれば良い、と主張しているのに対して、裁判所がこの主張を否定していることから、部門統括者の「管理監督者」該当性を否定しているようにも見えます。
けれども、裁判所がYの主張を否定したポイントは、Yが、②労務管理などの広範な権限を有しておらず、③待遇としても、残業代をもらえない分、かえって一般従業員よりも収入が減る場合があるなど、待遇が十分ではない点を重視している点にあり、Xが経営者の「分身」かどうかについて何ら判断を示していません。そもそも、会社組織では、経営者が有する様々な権限を従業員に権限移譲することで、組織的な活動を可能にしていますから、その点を見れば、何らかの権限を有する者は全員が「分身」と言えることになってしまいます。
他方、この事案では、②③が上記のとおりなので、仮に①を「部門統括」としても、Xがこれに該当すると評価するのは難しいでしょう。
したがって、裁判所が「分身」理論を否定したからと言って、ただちに「部門統括者」理論も否定したと評価すべきではありません。
このように見ると、この裁判例では、①について「経営者との一体性」を正面から認めていますが、「部門統括」を敢えて否定している、と評価することは難しいと思われます。
むしろ、本来であれば分社し、独立した会社にしてもおかしくないような部門の統括を任されている場合(部門統括者の最も極端な場合)を想定すれば、仮にその部門統括者が役員会のメンバーではなく、「経営者との一体性」が認められない場合であっても、管理監督者に該当しうるとすべきでしょう。なぜなら、労務管理者としての権限だけでなく、当該部門の予算設定や決算、事業の承認権限など、実態は会社経営者としての権限と責任を有することになるからです。
この裁判例でも、(経営者との一体性の判断要素としていますが)「損益管理、施設・設備管理、営業管理などの労務管理以外の事項に関する権限の好況も踏まえて」、「重要な職務と責任を有する立場」かどうかを判断するとしています。これだけ重要な職責を負うのであれば、労働時間規制に適しないからです。そして、この観点から見た場合には、統括を任された部門が実質的に独立した会社と同じであれば、ここで指摘されたような権限全てを与えられているのであって、経営者と一体でなくても、かなり「重要な職務と責任を有する立場」にあると評価できます。
むしろ、特に②について、経営者であれば有するべき権限は、労働時間だけでなく、極めて広範なはずですが、労働時間に特に限定していることを考慮すれば、②では足りない部分について、①経営者との一体性が補完している、と見ることができます。そうすると、①を「部門統括者」に置き換えた結果、本来、広く求められるべきだった広範な権限と責任があることを正面から問題にすることになるので、経営者との一体性がない場合も含まれるようになったとしても、「管理監督者」の本来の趣旨に合致した判断がなされることになるので、むしろ好ましいと評価できます。
したがって、一般的には、①「経営者との一体性」が問題にされますが、これを「部門統括者性」に置き換え、広範な権限と責任が与えられていればこれに該当する、とすることにも合理性があると思われます。
2.実務上のポイント
もっとも、「部門統括者性」の言葉だけが独り歩きすると、結局、中間管理職者が全てこれに該当すると誤解されかねません。
重要なのは、言葉ではなく、そこに含まれる内容です。
これは、上記のとおり、労基法41条2項が適用されること、すなわち労働時間規制に適しないこと、を意味しますから、「他人に使われている」状態ではなく、「他人を使っている」状態にある、と言い換えることが可能でしょう。
そうすると、②労務管理の権限が自分にある、という要素が重要になることが理解できますが、それだけでなく、(a)自分自身が経営者と同様の幅広い権限と重い責任を負担し、(b)経営の観点から幅広い問題について高い視点からの重い判断をしなければならない、ということが理解できます。②労務管理の権限だけの問題であれば、人事担当役員や人事部長がその典型例となってしまいますが、典型例は、人事担当役員や人事部長ではなく、経営者だからです。
このように見ると、「経営者との一体性」は(b)を重視していたのに対し、「部門統括者性」は(a)を重視していることがわかります。すなわち、単に部門を統括する肩書が与えられるだけでなく、経営者と同様の幅広い権限と重い責任を負担していることが、その内容として重要になってくるのです。
上手に説明すれば、「経営者一体性」が無くても、「部門統括性」の方向から「管理監督者性」を証明する可能性があることはわかりましたが、それは証明するルートが複数あることを意味するにすぎず、立証のレベルや、業務上の管理のレベルを下げるものではありません。
要するに、「他人に使われている」状態ではなく、「他人を使っている」状態にあることを、言葉を変えて説明しているにすぎませんから、いずれのルートを登るにしても、現実に相当の権限と責任が無ければ「管理監督者」に該当しません。単なる中間管理職者であれば、「管理監督者」に該当しない可能性が極めて高いことが、最近の裁判例の傾向から明らかになっていますので、小手先の説明方法でリスクに目を瞑るのではなく、実態に合致した適切なルールを作ることが必要です。
そして、実態とルールの合わせる方法としては、実態の方を変更し、広い権限と責任、高い報酬を支払うように変える方向と、ルールの方を変更し、「管理監督者」と位置付けることを止め、時間外手当を支払うように変える方向が、その両極端の方法として位置付けられます。実際にはその中間的な方法を模索することになるでしょうか。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。