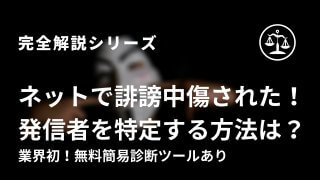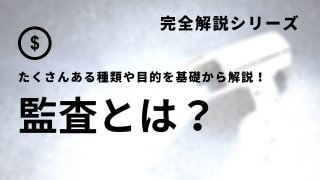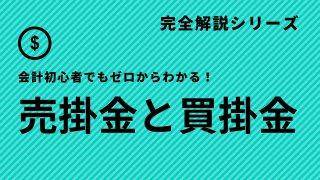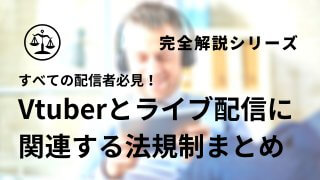0.事案の概要
この事案は、傷病休職者が復職を認められず、休職期間満了により解職された事案で、裁判所は解職を有効としましたが、休職期間中の「テスト出局」期間中の作業について、最低賃金相当の賃金の支払いを命じました。
1.はじめに
結論から言えば、この裁判例は、復職を希望する休職者への対応について、バランスの取れた結論を重視したように思われます。その分、理論的に詰めるべき問題が残されています。
2.NHKの運用
1つ目は、NHKのルールと実際の運用です。
傷病休職制度の多くは、休職期間が満了しても復職できない場合には、解雇・退職などの法律構成の違いはあるものの、労働契約が終了することになります。昔は、復職ができるかどうかを、医師の診断だけで判断することが多く、そのことがトラブルの原因でした。「働ける」「いや、働けない」という認定が論点となったのです。
けれども、そこに「プロセス」の発想が取り込まれました。
すなわち、例えば厚労省が示した、いわゆる「復職支援プログラム」(パンフレットの正式なタイトルは、「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ~メンタルヘルス対策における職場復帰支援~」)では、直ちに休職前の仕事を任せるのではなく、例えば最初は出社時間での出社だけをさせるなど、徐々に慣らしつつ、様子を見るような、段階的なプロセスを踏まえることが提案されています。これは、会社と従業員の双方にとって、現実を知る機会が与えられることにもなり、現状認識の食い違いによるトラブル発生の可能性が減る、等の紛争予防や紛争回避の効果も期待されます。
実際、この事案でもNHKは、従業員の「テスト出局」制度を設け、当該従業員にこれを適用し、復職可能性を慎重に見極めようとしていました。
このように、休職期間中は何も関与せず、復職の際にいきなり復職不可能と評価して労働契約を終了するのではなく、プロセスを重視した運用がされていたのです。
3.復職プロセスの位置付け
2つ目は、復職プロセスの取り扱いです。
NHKは、これを休職期間中の無休の訓練、と位置付けています。
もしこれを「業務」と位置付けて給料を支払うと、業務遂行可能であることを認めたことになってしまい、実際に復職を認めるべきでないときに拒むことができなくなる、という事態を懸念しているのでしょうか。
たしかに、復職プロセスの当初は、勤務時間に出社することだけを訓練するなど、とても業務と言える状況ではありませんから、それに対してなぜ他の従業員と同様に給与を支払うのか、不公平に感じる人もいるでしょう。
また、実際の訓練の負荷の程度や業務との類似性の程度に応じて、減額した給与を支払う方法も考えられます。特に、復職プロセスの後半になると、実際の業務に近い訓練になっていき、中には実際に業務をやってみましょう、という会社もあるでしょう。
そこで、全てではないにしろ、業務として扱い、給与の一部を支払う、という方法も考えられるのです。
しかし、裁判所は、「1日につき標準報酬日額の85パーセントに相当する額の傷病手当及び付加給付」が健保から支払われていると認定し、他方、支給される金額が傷病手当を上回らない限り傷病手当から控除され、結局、従業員が受け取る金額が同じになる、と認定しています。
そのうえで、経済的に見れば従業員にとって差が無いので、無給扱いでも良い、したがって無給とする合意も有効、と判断したのです。
つまり裁判所は、復職プロセス=業務でない=無給、という取り扱いを適法と評価しました。
4.最低賃金法の適用
3つ目は、最低賃金法の適用です。
すなわち、裁判所は、最低賃金相当の賃金として、合計15万円ほどの支払いをNHKに命じました。
「テスト出局」は、実際に成果物が業務として採用された課題提出物もあり、それが無休なのに数か月にも及んだ点が、「労働」として、最低賃金法の適用対象になる、と評価されたのです。
問題は、上記3のように、「復職プロセス=業務でない=無給」という取り扱いを適法としつつ、最低賃金部分について「業務である=有給」と評価した点です。
すなわち、一方で「業務でない」、他方で「業務である」として、評価が矛盾するようにも見えます。
また、上記3では、結局傷病手当から控除されることを有効性の根拠としていますが、最低賃金法が適用される場面でも同じことが発生します。裁判所は、ここで、既に傷病手当を受領している従業員について、最低賃金相当の賃金を健保に返還すべきことになるが、それでも受け取る権利はある、という説明をしていますが、結局従業員の手元に残らないのであれば、上記3と同じことのように思われるのです。
これらの、一見すると矛盾するような判断は、どのように矛盾しない、と説明するのでしょうか。
この点、裁判所は、法律構成の違い、と説明しているようです。
すなわち、上記3は、無休の復職プロセスの「合意」の問題であり、違法でないレベルであれば無効とはならないが、他方、4の問題は最低賃金法という、本人の意思に関わりなく強制的に適用される法律である、つまりこの事案では、「合意」に基づくルールと最低賃金法に基づくルールの両方が適用された結果である、という説明です。この観点からすると、従業員が受け取るべき最低賃金相当の賃金を、結局健保に返さなければならないとしても、それは法がそうしろと言っているからそうなるのであって、止むを得ない、ということになるのでしょう。
5.問題点
けれども、問題が一つ残ります。
それは、傷病手当における「労務に服することができない」(健康保険法99条1項)という要件です。最低賃金法が適用される、ということは、その範囲で労務提供していることになりますので、この要件が満たされないのではないか、したがって傷病手当の支給が違法になってしまい、従業員が健保に支払うべき金額は、(最低保証相当額ではなく)既に受領した傷病手当全額なのではないか、という疑問です。
もし、傷病手当が支払われる、という結論を維持するのであれば、上記「労務に服することができない」という言葉の意味は、「労務一般」を意味するのではなく、「当該労働者が従前行っていた特定の労務」という意味に解釈するのかもしれません。
しかし、この解釈を取ってしまうと、病気やけがのために軽度の業務に変更され、仕事を続けた場合にも、傷病手当が発生することになります。すなわち、給与が大幅に減額した場合でも、この会社の場合、元の給与の85%との差額を傷病手当として受け取れることになるのです。けれども、実際にこのような運用が行われている様には思えません。
あるいは、「労務に服することができない」というのは、「正式に復職できない」という形式的な意味であり、他方、最低賃金法は、現実的に労務を提供していたかどうか、という労務実態の問題である、という整理もあり得ます。明示はしていませんが、この裁判例も、このように整理しているのかもしれません。
このことで、仮に要件の解釈はできたとしても、問題は残ります。
結局、最低賃金相当の賃金を受け取っても、従業員はこれを健保に返さなければならない、そんなことのために無理な解釈をする必要があったのか、という点です。
6.おわりに
もし、復職プロセスを、2の冒頭で示したような取り扱い、すなわち、その業務の内容に応じて段階的に給与が増える「業務」としたらどうなるでしょうか。
賃金の減額になりますので、会社が一方的に行うことは、就業規則などで事前に定めない限り難しそうです。
しかし、合意に基づく場合には、それが「真の自由意思」であれば、有効とされる可能性もありそうです。この場合、従業員は傷病手当が受領できない、と評価すべきですから、あまりにも低額だとトラブルの可能性が高まります。相当の割合の給与を支払うべき、相当の難易度の業務を試験的に行わせる段階になってから適用することになるでしょう。
法律構成としては、復職可能性を見極めるための暫定的な有期雇用、ということでしょうが、復職できない場合に、この暫定的な契約にも解雇権濫用の法理が適用されるのでしょうか。また、復職するレベルの能力はないが、復職プロセスでの軽度の業務を行うレベルの能力はある、という微妙な評価を前提とする制度が、実際にうまく機能するのでしょうか。
復職プロセスによる軟着陸が、実務上、それなりに広がり始めている状況で、復職プロセスに関する法律構成や実務運用について、より使いやすく整備されることが望まれます。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。