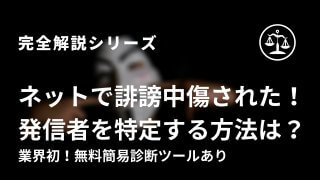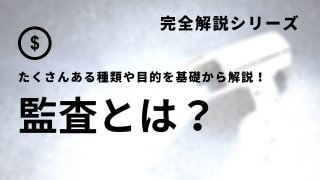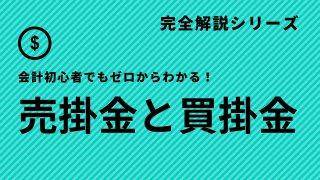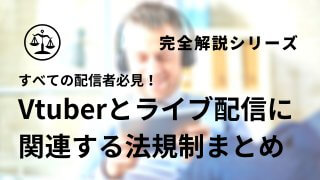0.事案の概要
この事案は、職場での従業員同士の喧嘩によって後遺障害を負った原告Xが、加害者Y1と会社Y2に対し、損害賠償を請求したものです。裁判所は、Y1の責任を肯定しましたが、Y2 の責任は否定しました。
ここでは、Y2の責任について検討します。
1.使用者責任
Y2の責任を認める場合の法律構成の1つ目は、民法715条の使用者責任です。
これは、従業員と会社の場合が典型ですが、従業員が「事業の執行につき」加えた損害を、会社も責任を負う、というルールです。「事業の執行につき」という言葉が抽象的で、幅のある概念であるため、①事業の執行を契機とし、②密接な関連を有する場合である、という判断枠組み(ルール)が、裁判所によって示されています。
従前、この「事業の執行につき」は、かなり広く認められており、例えば同じ従業員同士の喧嘩であっても、「鋸を貸してくれ」と言ったところ鋸を投げつけた同僚に暴行した事案や、勤務中の飲酒を注意されたバーテンが同僚を殺害した事案、印刷機のトナーの交換の際の口論が暴行に発展した事案、等で「事業の執行につき」該当性が認められています(労判1208.62~)。
これらとの違いが問題になります。
確かに外形上は、緊急コールのコンセントが外れていたことが口論のきっかけですので、①事業の執行を契機としており、②それを正そうというやり取りが原因ですので、事業との密接関連性が存在するようにも見えます。
ところが、裁判所はこれは単なるきっかけにすぎず、喧嘩の原因は暴行以前からの個人的な感情の対立、嫌悪感の衝突、挑発的侮辱的な言動にあること(②)、口論のきっかけとなったミスも、業務として指示されていたものではないこと(①)、などから、①②を否定し、「事業の執行につき」を否定しました。つまり、①は業務の外形的な面から(与えられた業務ではない)、②は喧嘩の実態から(私的な感情が原因である)検討していると言えるでしょう。
「事業の執行につき」の該当性を認めた裁判例に比較すると、この裁判例との違いは相対的な違いにすぎず、質的ではなく量的な差でしかありませんが、形式と実態の両方から検討している、と整理してみれば、今後の判断の一助になるのではないでしょうか。
2.安全配慮義務違反
Y2の責任を認める場合の法律構成の2つ目は、Y2自身の直接責任(安全配慮義務違反、民法415条・709条)です。
これは、Y2に過失があることが条件となりますが、「過失」も曖昧な概念ですから、実際には、「予見義務違反」「回避義務違反」が検討されます。つまり、「気付くべきだった」「避けるべきだった」という状況になれば、「過失」が認められます。
この点についての裁判所の判断は、X入社後3回目の勤務日の事件であること、XとY1が顔を合わせる機会は1日あたり1~2時間程度で、それまで合計4時間程度にとどまること、それ以前にY1が暴行した事情はないこと、XとY1の間が険悪な状態になっている報告はないこと、などから、Y2にはY1がXに暴行する可能性を予見不可能だった、として過失を否定しています。
この点は、事実認定として違和感なく理解できるところでしょう。
3.実務上のポイント
会社の安全配慮義務違反は、従業員の健康管理の問題として、最近特に重大な問題領域となっています。言うなれば、会社はどこまで「お節介」であるべきなのか、という問題です。仕事のストレスがかかる場面での気配りは、メンタルについての責任にも関わるので、非常に慎重に対応しなければなりませんが、この事案のように、従業員同士の個人的な憎悪感情まで会社がケアしろというのは、さすがに行き過ぎでしょう。
このように、会社に何らかの原因(ストレスを与えている、など)があるかないか、が1つのポイントである、という見方も、判断の分かれ目を見分ける1つのヒントになると思われます。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。