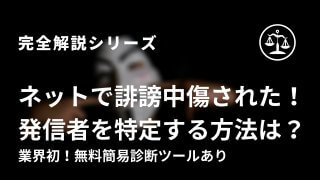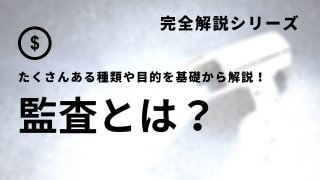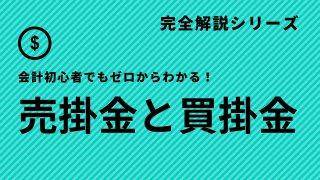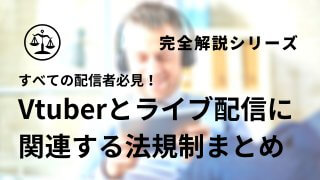0.事案の概要
この事案は、「中小企業等協同組合法」(中企協法)に基づく企業組合Yと、その組合員Xの間でのトラブルです。Xは、自らが労働者に該当するとして、組合離脱後に、未払残業代の支払いを求めましたが、裁判所はXの労働者性を否定し、請求を棄却しました。
1.判断枠組み(ルール)
まず、裁判所は、「企業組合」という法形式だけで労働者性の有無を判断しない、として実態に基づく評価が行われることを明確にしました。
これは、形式や外観よりも実態を重視するという労働法の特徴を表しています。
そのうえで、労働者性を判断する判断枠組みは、最高裁判例などによって明確にされていないものの、いわゆる「労働基準法研究会報告」(昭和60.12.19)の示した判断基準をベースにしています。
すなわち、①労務提供の形態(a仕事を断れるか、b指揮命令されるか、c拘束されるか)、②賃金性(労務への対価か)、③その他(a事業者か、b賃金の額)を総合的に判断して評価するのです。
注目されるのは、①②だけでなく③も考慮する理由として裁判所が、①②が「明確性を欠き」、これだけでは労働者性の判断が「困難な場合もある」ことを挙げている点です。簡単に割り切れない場合がある、ということが前提になっています。また、従業員性を従業員に近いかどうか、という観点からだけでなく、反対に、事業者から遠いかどうか、という観点からも見る、つまり両方から光を当てる、という評価方法が示されました。1方向からだけでなく、2方向から見ることで、距離感も客観的になりますので、非常に興味深い視点と感じます。
2.事実(あてはめ)
たしかに、①②だけでなく、③も合わせて考慮する必要性、すなわち①②の曖昧さは、この事案から見るとよく理解できます。
すなわち、Xが主張している以下の点を見れば、従業員性が認められるようにも見えるからです。
1:配達コース、配達量などが理事から指定される
2:寄り道する場合は、その都度報告が必要
3:朝集合し、朝礼に参加し、帰着後も伝票整理などの業務を行っていた
4:休暇取得のために2週間前までに申告が必要
5:懲戒処分同様の制裁(顛末書、アルバイトへの降格、減給処分)
6:商品キャンペーン販売を指示される
7:生協の保険事業に従事させられる
8:「持ち上げ手当」「マンション手当」など、配達コースに応じた手当が支給される
9:手袋や制服が支給され統一されていた
10:Yは労基の指摘で残業代を払ったことがある
一応、それぞれについて裁判所は、従業員性を否定する方向での検討を加えています。
まず一般論として、業務指示などを拒めない場合は、一応、指揮監督関係を推認させるけれども、包括的な仕事を受諾した結果、個々の仕事の拒否権が制限される場合もあるため、契約関係も見なければならない、と指摘しています。
それぞれについての、裁判所の評価の概要は以下のとおりです。
1:Xも参加した運営委員会で協議し、実際変更もあり、拒否できないことを積極的に評価できない。安全運転のためであり、業務内容への指示ではない。
2:寄り道は禁止されておらず、懲戒対象でもない。
3:配達に遅れないための朝の集合や、確認などの朝礼、全体を把握するための報告は、必要性あり。遅れても懲戒対象でなく、終了後順次解散になっていた、など、拘束性も小さい。
4:業務の調整や引継のためのものであって、労務管理ではない。
5:少人数組織でサービスの質を維持するために必要、指揮命令やその担保のためではない。
6:販売目標を達成しなくてもペナルティーなし。
7:生保との契約に基づくもので、関係ない。
8:メンバー間の公平を確保する措置が、当然に賃金性を帯びるわけではない。
9:事業の必要性から統一したのであって、試用従属関係を是認する事情ではない。
10:労基の判断と前提が違うし、当時知識がないから残業代を払っただけで、労働者性を認めたことにならない。
その上で、③運営会議でXらも等しく発言しており、事業者性が否定されない、としています。
このように、①②だけだと、判断が難しいが、③(すなわち、事業者とされている契約上の立場が否定されるような運営実態になっていない)も考慮すれば、従業員性があると評価できる、と思われるのです。
3.実務上のポイント
①②従業員性は、実際に働いている実態から評価されますが、③事業者性は、事業者の根拠となる契約形態からスタートし、それが実際の運用により、事業者性が否定されるような状態になっているのかどうか、という評価をしています。
この①~③を総体で見ると、結局、労働者ではないとする法律構成をひっくり返すだけの実態があるのか、という判断構造になります。すなわち、契約書の法律構成によって事業者性が説明できれば、それを従業員性を主張する側がひっくり返さなければならない状況にある、と評価できそうです。
問題は、このような構造が一般的なことかどうか、という点です。
この点について、現時点ですぐに一般企業でも同じ構造である、と位置付けるのは尚早と考えます。それは、この事案が中企協法に基づく企業組合に関する事案だからです。すなわち、法律自身が構成員を組合員と位置付けているのに、労働法の関係では労働者性が認められることになると、企業組合というの構成員には、組合員として公平に処遇すべき面と、従業員として特に優遇すべき面の両面が備わることになってしまい、企業組合構成員の処遇が難しくなってしまいます。そうなると、企業組合という制度が使われなくなりかねません。
このように、契約書の法律構成が重視されるような構造は、Yが企業組合だからこそ、という評価も可能であり、一般企業とは前提が異なる、と評価する余地があるのです。
※ JILAの研究会(東京、大阪)で、毎月1回、労働判例を読み込んでいます。
その中から、特に気になる判例について、コメントします。
スタートアップドライブでは、労務や労働問題の相談に最適な専門家や法律事務所を無料で紹介します。
お電話で03-6206-1106(受付時間 9:00〜18:00(日・祝を除く))、
または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。

 赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。